みなさんは人生を楽しめていますか?
私は、楽しいこともあるけど、つらいこともかなり多いなぁと感じています。特に、仕事が忙しい時期は朝早くに家を出て、必死に仕事を片付けていき、気づいたら夜遅くになっていることも多く、へとへとです…そして、同じようなことが繰り返される毎日に若干嫌気が指しています。もっと楽に生きられないんですかねぇ!?
私は今アラフォーなので、普通にいけばあと25年以上この生活が続くことになります。それに気づいたときはゾッとしました。自分は耐えられるのだろうか?そんな思いの中、久々にニーチェの考え方を学びたいと感じました。今の自分になにかヒントを与えてくれるのではないかとちょっと期待している私がいます。
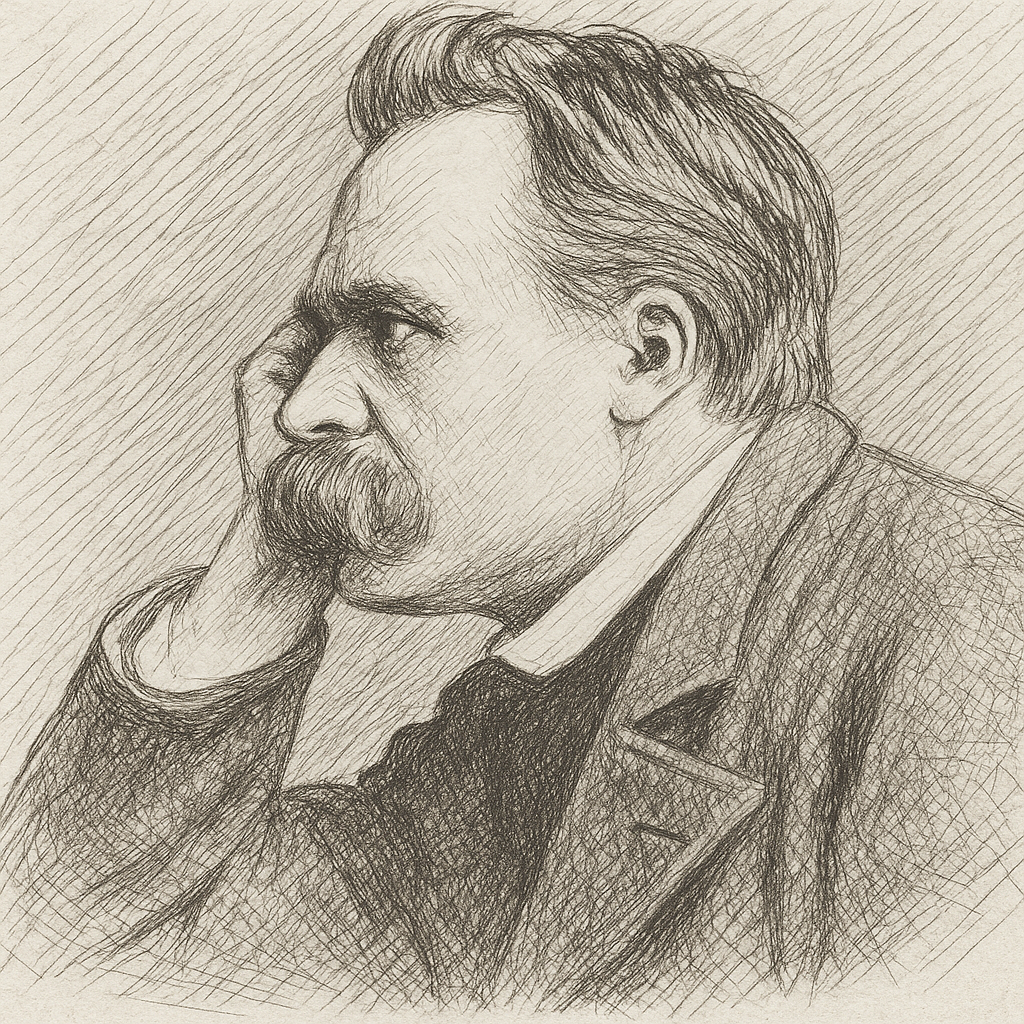
そして、生き方に悩んでいるのは自分だけではないと思います。ですので、学んだことをみなさんにも共有できればと思います。最後まで、お読みいただけると幸いです♪
それでは、キーワードを中心にニーチェの思想に迫っていきます!!
ニヒリズム
ニーチェは、「次の2世紀はニヒリズムの時代である」と予言しています。
彼は、ほぼ19世紀後半を生きた人なので、20世紀と私たちが今生きている21世紀のことを言っています。

ニヒリズムは「虚無主義」と訳されたりしますが、ニーチェはこれを「絶対的な価値がなくなる」という表現で使っています。確かに、現代において多くの人は何を信じて生きていいのか分からなくなっているようにも見えます。ニーチェの生きた時代の前くらいまでは、神という絶対的な存在が固く信じられており、その教えに従って生きていればよかった。しかし、現代においては、宗教の力は弱まり、本気で信じる人も少なくなってしまった。その中で、時代の変化のスピードが早くなり、デマも含めて大量の情報も溢れている。多様性が重視され、何が正しいのか、正義なのか曖昧なものになってきている。そういう意味では、平均台の上を全力で駆け抜けているようなイメージですかね!?だから、そこから落ちてしまう人もたくさんいる。生きるってしんどいなぁと多くの人が感じているのです。
神は死んだ
これも有名な言葉ですね!?
ヨーロッパを中心にキリスト教が広まって、中世の頃までは神の教えが絶対でした。しかし、19世紀には、科学の進展(ダーウィンの進化論など)や啓蒙主義の影響で、キリスト教の教義に対する信仰が弱まっていきました。そのような状況のことを言っています。同時に、絶対的な真理に対する人々の信頼がなくなったことも表現した言葉となっています。

繰り返しになっている部分もありますが、絶対的であった神が死んでしまうと、当然のように人々の中に混乱が生じます。なぜなら、神が信じられていた時代には、神の言葉がそのまま真理となるので、疑う余地はなかった。つまり、迷いがなかったのです。しかし、神が死んでしまったら、今度は疑うことしかできなくなってしまったのです。人間って意外と自分自身で真理を判断して生きていくのは難しいんですよね。だから、現代においても、テレビやインターネット、SNSなどで専門家(下手すると全然専門家のレベルにない人)たちの意見を鵜呑みにしたり、占いや迷信を信じたり、人の意見に同調するだけの人も結構いますよね!?何か絶対的なものに頼りたくなるのが人間なんですよね…その方が楽だから
ここまでの話をまとめると、神が死んだことにより、絶対的な価値がなくなる状態、つまりはニヒリズムの次代となった。その中で、人々は不安定な状態に置かれ、混乱している。それが、21世紀においても続いているということではないでしょうか。
ルサンチマン
ニーチェを学んだ方には、お馴染みの言葉ですね。「逆恨み」とか「妬み」といった意味があります。ニーチェは、力で勝負できない人が、相手を何とか引きずり降ろすために、自己正当化すると考えていました。そして、キリスト教の思想に由来するヨーロッパの道徳は弱者を正当化するもの(奴隷道徳)であるとして、ニーチェは批判をしています。
教会組織が民衆を利用し、彼らのルサンチマンを煽りながら、強者を叩き潰して、教会組織による社会的な支配階層を作り上げてきたとニーチェは見ています。

現代においても、政治家やテレビに出ている芸能人などが、弱者に寄り添うふりをして、自らの権力や名声を増大化しているケースも見るけられるのではないでしょうか。
永遠回帰
これは、自分の生きてきたことが無限に繰り返されるということを意味しています。元々ニーチェは、ショーペンハウアーの影響を強く受けており、生きることをただの苦しいことであると捉えていました。
しかし、生きることが苦痛でしかないのなら、何で生きているのかと言われてしまうとそこに矛盾が生じてしまいます。だから、ニーチェはその考えから脱却しなくてはならなかった。そこで、生きることは同じことの繰り返しであると考えたのです。
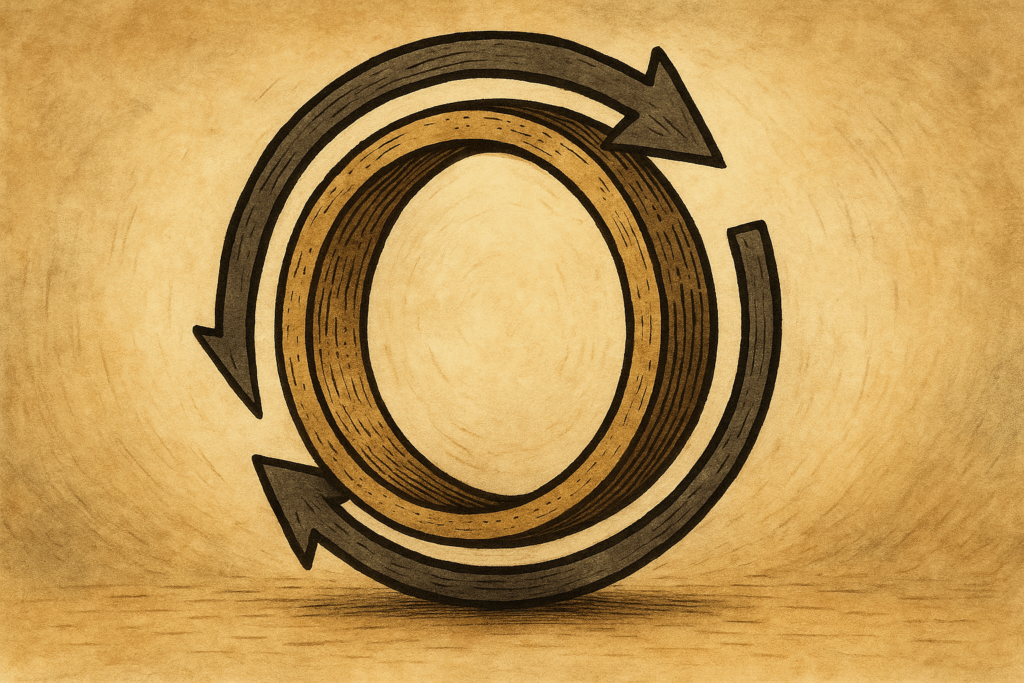
確かに、多少の違いこそあれ、同じようなことがぐるぐると回り、いつの間にか歳を重ねてしまっているような気がしませんか?私だけでしょうか?このまま過ごしていると、あっという間に何もない人生が終わってしまうのではないか…そんな恐怖が時に襲ってきます。私は今アラフォーですが、30代後半から、そんなことを考え始めるようになりました。
重要なことは、これは単なる運命論ではなく、その人生を繰り返してもよいと思えるほど徹底的に肯定することを問う倫理的な試練なのです。これに「はい」と答えられる人が超人なのです。
超人
このように、「人生は同じことの繰り返しなのに、それでも生きるのか?」とニーチェは私たちに問いかけています。そして、そんな退屈な人生に耐えられる人を超人としました。ここで超人とは何を意味しているか気になりますよね!?実は、はっきりとしたことは分かっていないのですが、ヒントとなる発言もあります。
「人間とはサルから超人へと向かう中間にあるもの」
また、ニーチェには人間の変化を語る表現があります。それは「精神の3つの変化」と呼ばれるもので、一番最初は駱駝であり、重荷を背負っている。次に、獅子になる。獅子は自由になるが批判的であり、いろいろな人に吠えかかり、噛みついていく。そして、最後に子供になる。

なぜ最後が子供なのでしょうか?
私なりの結論
ここからは、私の意見になっていきますが、要はニーチェは、人生は同じようなことの繰り返しなんだとしました。そんな人生を生きていたいのか?
個人的には、しんどいと思ってます。ただ、人生のいつだったら、何度繰り返してもいいかなぁと考えてみたら、幼稚園児とか小学生の頃かなと思います。あの頃は、目の前の遊びに夢中だった。心配もなかった。ただただ、また明日も友達と遊びたいなぁと思えていた。大人になってからも、野球に熱中していた頃は、毎年開催される大会に出るのが楽しみだった。社会人になって、野球するのが楽しみだなんて、子供みたいですよね!?

でも、それが1つの答えなのではないかと思ってます。子供のように何かに熱中する。野球でもいいし、ゲームでもいい、友達との会話でもいい。もちろん仕事でもいいと思います。そういうことができる人は人生を肯定的に生きられるのではないでしょうか?
もちろん、100%やりたいことだけやって生きていくことは困難です。人生はそんなにあまくはない。でも、やりたいことができない人生なんて嫌ですよね。実際には、忙しすぎてやりたいことができない人、もはや自分が何をしたいのかも忘れてしまった人も多くいると思います。私もそうなりかけていました。
結論としては、毎日の生活の中で、自分が本当にやりたいことをできる時間を増やしていく。それを優先してあげる。その時間を心から楽しむ。まさに子供のように熱中する。それこそが今のつらい人生を明るくしてくれるのではないでしょうか!?
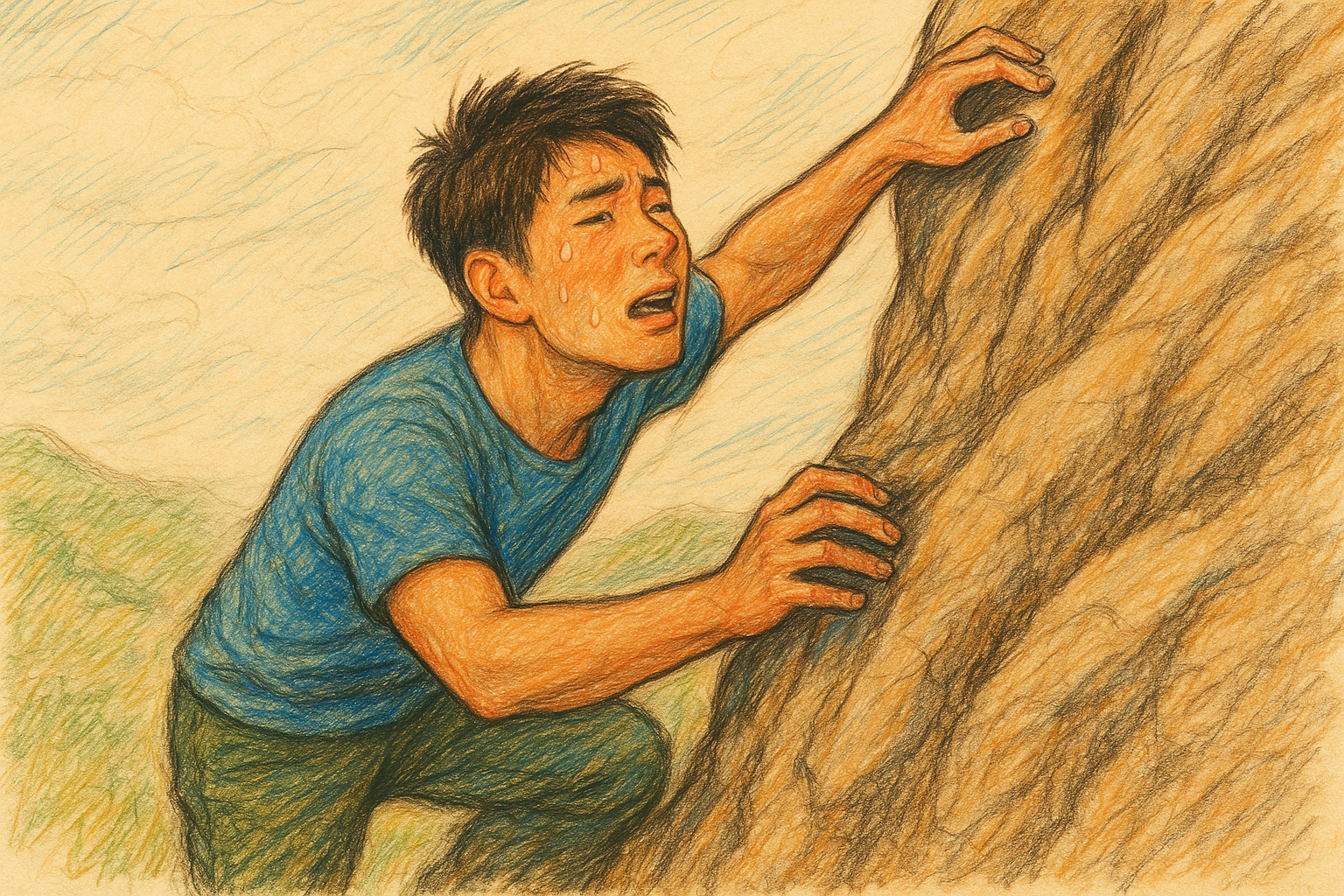


コメント