唐招提寺の散策を終えて、そこからどんどん北に向かっていく。
最終的な目的地は西大寺となるが、その途中に喜光寺が存在する。時間もあるし、せっかくなので、寄っていくことにした。なお、当寺は奈良では珍しく、仏像も含めて写真を撮っていいため、貴重な記録を残すことができた。
また、喜光寺の前に垂仁天皇陵が存在する。のどかな田園風景の中に急に出てくるのでびっくりだ!巨大な前方後円墳とのことであるが、上空からじゃないとただの島に見える…




ちなみに、垂仁天皇は「殉葬から埴輪への転換」「常世の国から橘を持ち帰らせた伝説」など、文化や制度の始まりに関わる物語が付与された人物であり、歴史的実在は不明ながら、日本神話・古代伝承において重要な役割を持つ天皇であると伝わる。
『日本書紀』には、垂仁天皇の命によって大和の埴輪の起源が語られており、殉葬を禁じて代わりに埴輪を用いたとされている。そういった点など、温厚で慈愛に満ちた性格として描かれることが多い天皇である。
また、家臣である田道間守(たじまもり)に「枯れずに香る不老不死のような果実(橘)を探してきなさい」と命じたという話もある。どこにいって探すかというと、「常世の国(とこよのくに)」、つまりは、海の彼方にある理想郷、不老不死の国から「その果実を持ち帰れ」と命じたのである。この伝承は「橘=ミカンなどの柑橘類」が日本に伝わった起源を説明する神話のひとつとされている。

じっくりと眺めていたいところであるが、丁度お腹が痛くなってきた頃で、トイレにどうしてもいきたかったので、急いで写真を撮って、その場を後にした。
喜光寺とは



養老5年(721)行基はこの地に住んでいた寺史乙丸という人物から平城京右京三条三坊の土地の寄進を受け、翌年にお寺を建てた。これが喜光寺となる。創建当時は、その土地の名前から「菅原寺」と名付けられていた。
行基は、聖武天皇に認められ、布教活動・社会事業に尽力した人物である。そして、人生最後の大仕事として、東大寺大仏造立にとりかかった。そのさなか、聖武天皇が菅原寺を訪れ、本尊をおまいりしたところ、本尊から不思議な光が放たれた。聖武天皇は大いに喜び、「歓喜の光の寺である」として、「喜光寺」という名になったと伝わる。
なお、東大寺を東大寺を訪れた際の記事はこちら!
06 東大寺とは?奈良の大仏と壮大な伽藍に出会う歴史散歩 | くま吉の歴史散歩ブログ
境内を散策
境内に入るとまず本堂(重文・室町時代)が見える。
実は、東大寺造営の際、行基はこのお寺の本堂を参考にしたため「試みの大仏殿」とも呼ばれる。創建当初の本堂は、明応8年(1499)に焼失してしまった。その後、室町時代、天文13年(1544)元の場所に再建された。

本堂の内部には、本尊である阿弥陀如来像(重文・平安時代)などが安置されている。金箔が剥がれていてきれいな状態とは言えないが、その分歴史の重みを感じることができるのではないだろうか。





当寺のもう一つの目玉は、行基堂である。ここに行基菩薩坐像が安置されている。

行基は、喜光寺を拠点として、東大寺大仏を造営し、全国を行脚、各地に国分寺を建立した。さらに、池や堤を築き、水路や橋を架け、民間伝道や社会福祉活動をしたことから、民衆から「菩薩」と呼ばれ信仰を集めた。
また、天平17年(745)には、聖武天皇から日本で最初の大僧正に任ぜられるなど、奈良時代を代表する高僧であった。

行基像から、芯が強そうな人物だったのではと感じ取れる。私も多くの人から尊敬を集められるような人間になりますと誓って、その場を後にした。さすがに、「菩薩」と呼ばれるような人間にはなれないと思うが…
まとめ
喜光寺は、小規模なお寺であったけれども、行基や叡尊といった名だたる僧と深い関係があるお寺であることを学ぶことができた。
また、平安時代の阿弥陀如来も祀られているなど、見どころもあったので、なんやかんや訪れてよかった。特に写真に力を入れている私にとっては、撮影OKだったのも嬉しかった。
なお、6月中旬~8月上旬には、約80種類・250鉢の蓮が鉢で飾られているので、タイミングが合ったらそれを目的に訪れるのも良い♪

それでは、今回の旅の最後の目的地である西大寺へと向かっていく。

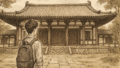
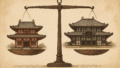
コメント